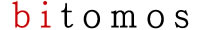過保護な親の影響は?★ドラマ「過保護のカホコ」で子育てを考える

少し古いですが2017年7月~のドラマとして日本テレビ系列で放送している「過保護のカホコ」。このドラマはいろいろな見方があると思います。ここでは過保護ってどういうこと?から考えてみます。
過保護って悪いの?親の過保護で子供はどう育つ?親と子のベストな関係って?子育て中のお母さんもぜひ一緒に考えてみませんか。
ドラマ「過保護のカホコ」の親はこんな過保護お母さん
主人公大学生のカホコは両親との3人暮らしです。朝はお母さんの手作りお弁当、毎日の洋服のコーデはお母さんにどっちがいいかお伺い、毎朝、駅までお母さん運転の車で送ってもらいます。何でもお母さんに相談して夜は毎日、お母さんと一緒にカホコの小さい時のビデオを鑑賞します。
カホコのお母さんは「 カホコはお母さんの言うとおりにしていたら間違いないんだから」と口癖の様にカホコに言います。ある日、よっぱらったカホコが大学の友達の麦野くんに家まで送ってもらった時には、お母さんはお礼も言わずに、二度とカホコに会わないでと言い放ちます。
それに機に初めてお母さんに反発するカホコ。お母さんとの仲もギクシャクしてきますが…。
この様なストーリーで展開していきます。
カホコのお母さんの過保護ぶりをまとめてみました。
●毎朝お弁当はお母さんの手作り
●毎朝、駅まで車で送る
●毎朝、娘の洋服を決めてあげる
●娘の交際相手に大反対
●「カホコはお母さんの言うことを聞いていればいい」と言い切る
●娘の恋愛に口出ししてくる
ドラマの中でカホコが好きな麦野くんの「オマエ、大学生にもなってお母さんにお弁当作ってもらってんの?」というセリフ。筆者と一緒に観ていた我が娘は「大学生でお弁当作ってもらったら、過保護なの?」と言っていましたが。
●出来るときはお弁当を作ってあげる。
●家にいるときは駅まで送り迎え。
●出かけるときに誰と?どこに?って聞く。
●一緒に洋服を買いに行くと「これは?」と言いながら、コーデしてしまう。ダメかな…。
親の過保護とは

「子供を育てている中で子供自身が出来ることでも親があれやこれや手出しをしている状況」
過保護の定義を言えばこの様なことです。どんな親にも心あたりがある事かもしれませんが、その子供の年齢に応じているか、過度になっていないかどうかでも過保護の度合いは変わってきます。
例えば、赤ちゃんの時に離乳食が始まったころは、上手に自分でスプーンなどを使って食べられないので親が食べ物を口に運んであげます。
幼稚園に入る前の年齢では着替えの時にボタンなどはまだ自分でスムーズにかけられないので親がやってあげます。
子供が出来る事でもつい親が手出しをしてしまうのが過保護というのは間違いないです。そしてそういう過保護な親の影響は必ず、子供に影響を与えることになります。
ここでよく聞く「過干渉」という言葉もありますが、過保護と過干渉の違いはどういうものなのでしょうか。ちょっと触れたいと思います。
過保護と過干渉の違いは?
「親の過保護」よりも、もっと子供に与える影響があると言われているのが「親の過干渉」です。
「親の過干渉」「過干渉な親」とは、子供に対していろいろな形で干渉していきます。大きく分けて「直接的」なものと「間接的」なものがあります。
直接的な親の過干渉
●「こうしなさい」「あ~しなさい」
●「あれはダメ」「これはダメ」
●「これにしておきなさい」
などと、子供の意見より親の意見に従わせるように干渉することです。
間接的な親の過干渉
●イヤならイヤって言っていいのよ
●親は応援するだけであなたの意見を尊重するわ
●あなたの思い通りにしてみなさい
などと言いつつ、子供が親の思いとは反対の意見や行動をしたり、子供が親のアドバイスを受け入れない状況になったりすると…過干渉の親は次のようになります。
●がっかりする
●ため息をつく
●イライラする
などの状態になり、直接、口で言わなくても子供を知らず知らずのうちに、子供をコントロールしてしまう間接的な過干渉の状態を作っていることがあります。
この二つの矛盾したメッセージの状況を【ダブルバインド(二重拘束)】といいます。
過干渉で気を付けたいのは…
長い間のダブルバインドの状況では、心理面においての苦痛、そして葛藤が生まれることで精神的な不調になることがある、または陥りやすくなってしまうという報告が【社会学者・文化人類学者のグレゴリー・ベイトソン】の研究によりされています。
過保護な段階ではまだそこまでいっていない…でも過保護の延長上に過干渉があることも忘れないほうがいいですね。

過保護と過干渉の違いと影響に関する補足
過保護と過干渉、どちらも親の愛情から生まれる行動ですが、その結果として子どもの精神に与える影響は大きく異なります。過保護は子どもを危険や失敗から守りたいという親の願望からくるものですが、過干渉は親が子どもの意思や選択を過度にコントロールしようとする行動です。ここでは、これらの行動が子どもの自己肯定感や社会での適応能力にどのような影響を及ぼすのか、深掘りしてみましょう。
自己肯定感への影響
過保護な環境で育った子どもは、自らの能力に対する信頼を十分に育むことができず、自己肯定感が低下する傾向にあります。常に親が代わりに問題を解決してくれるため、自分自身で挑戦し、失敗から学ぶという経験が不足します。これは、将来的に自分の決断を下す際の不安や恐怖につながる可能性があります。
一方、過干渉は子どもが自己の意見や感情を表現することを抑えがちになります。親が「正しい」と判断した方法や選択のみを強制することで、子どもは自分の感情や意見が価値を持たないと感じるようになり、これが自己肯定感の低下に直結します。
社会での適応能力への影響
過保護によって育った子どもは、社会に出た際に自立する能力が欠けることがあります。学校や職場などでのチームワークや、異なる意見を持つ人との対話に苦労するケースが見られます。このような子どもは、自らの意見を持ち、それを他人と共有することに不安を感じるため、社会的な場面で適応するのが難しくなります。
過干渉がもたらす社会での適応能力への影響は、意思決定の不自由さにあります。親からの過度な干渉によって、子ども時代から自分で決断を下す機会が少なかった人は、大人になっても他人の意見に依存しがちです。自分自身で選択し、その結果に責任を持つことの大切さを学ぶ機会が減るため、社会的な自立が困難になります。

親の過保護が生む状況
ここで、「もしかして自分は過保護な親?過干渉な親?」と思った時に、その様な状況にしてしまう親の気持ちと、子供への影響をみていきましょう。
親が意識していなくても、または子供も意識していなくてもこの様なことを生んでいるということがあります。
過保護の親の気持ち

過保護の親に気持ちはどういうものなのでしょう。親が子供に愛情を向けるのは無償の愛として当たり前のことですが、ちょっと違った親の愛情に対しての考え方や思いがあるようです。間違った愛情表現や偏った愛情表現も問題なんですね。
過保護や過干渉の親は決して「自分の子供を支配してやろう」などと思っているわけではありません。むしろその逆で、多くの過保護や過干渉は親は「自分の子供が傷つかないように、失敗しないようになど守ろう」と、言い換えれば子供の意思の先回りをしてしまう状況です。
親はそれまで生きてきた人生の中で、いろいろな失敗などを含めて経験をしてきています。そしてその中でも過保護・過干渉の親は嫌な思いをして傷ついたことや、苦労したこと、失敗したことに関して子供に同じ思いをさせたくないという心理が強く働きます。
ただこの親の思いは言い換えると、次のように子供に届いていることがあります。

子どもの成長と自立を妨げている
そしてそれは…
 「嫌な思いをするあなたは受け入れられない」
「嫌な思いをするあなたは受け入れられない」
「傷つくあなたは受け入れられない」
「苦労するあなたは受け入れられない」
「失敗するあなたは受け入れられない」
親は意識しなくてもこの様なメッセージを子供の心の奥の方に届かせてしまいます。これは子供も意識してそう感じているわけではないところが大きな問題です。
もっと言えば、「あなたはそのままではダメ」という子供自身を否定になってしまいかねません。
ここで子供の中に育っている「インナーペアレント」についてご紹介します。
インナーペアレントとは?
過保護や過干渉による子供への影響については「子供は自分の親のものの見方に影響されて自分の中の<インナーペアレント>が形成されると言われています。
インナーペアレント=自分の中の親・自分の内にある親という意味になります。生まれてから育ってきた環境の中で親と接し、親の考え方やものの見方が子供に大きな影響を与えて作られてきた子供の内にあるものということです。
それがインナーペアレントになります。子供の成長の過程で大切なのはインナーペアレントは受容的に育てていくことです。
そして子供自身も自分を受容的に見つめることが大事になります。
そこで受容とはどういうことでしょう。
受容(ジュヨウ)とは 、受け入れて、とりこむこと。デジタル大辞泉
ここでは子供が自分自身の思いを、または親が子供の「思い」を受け入れるということになります。受容は相手を否定したり、評価をしない接し方、考え方です。
言い方を変えれば、受容的に形成されていないインナーペアレントは、親の過保護・過干渉の影響大だということです。
親の過保護が子供に与える影響

子育ての中で親が与える子供への影響は<受容的インナーペアレント><非受容的インナーペアレント>で違いがあります。先ほども書きましたが、大切なのはインナーペアレントは受容的に育てていくことです。親が過保護・過干渉では、子供のインナーペアレントは受容的ではないことが多いようです。
「過保護な親」のもとで育てられた子供は「自分が親に受容してもらえていない」ということを自覚していないのでインナーペアレントも自分がわからないうちに形成されてしまいます。
「自分の好みで何かを選ぶ」「自分で感じた感覚を大切にする」「自分で決断する」という事の経験が少なくなってしまうということなので、それは主に次のようなことに繋がってきます。
●自分に自信が持てない
●失敗することに過敏になる
●自分の決断が出来なかったり、自分の決断に過剰に不安になり、怖がる様なところがある
過保護な親の元で育ったとしても大丈夫!そこから子供はちゃんと自分を見つめることができる自分になれます!さてどのようにするのか見ていきましょう。

子ども自身の自己受容の仕方に関する補足
自己受容は、自分自身を理解し、受け入れることから始まります。この過程は、子どもや若者が自分の感情や思考、行動を受け入れ、それに対する自己評価を高めることに繋がります。ここでは、自己受容を深めるための具体的な方法やステップをいくつかご紹介します。
ポジティブな自己対話を実践する
自分に対して優しく、肯定的な言葉をかける習慣をつけましょう。例えば、「失敗しても大丈夫、次はもっとうまくいくよ」と自分自身を励ますことで、自己受容の感覚を強化します。ポジティブな自己対話は、自己肯定感を高め、挑戦する勇気を与えてくれます。
自分の感情を認識し、表現する
自分の感情を素直に認め、それを表現することも自己受容に繋がります。喜び、悲しみ、怒り、不安など、さまざまな感情を「そのままの自分」の一部として受け入れましょう。日記を書く、信頼できる人と話す、アートや音楽を通じて感情を表現するなど、感情を外に出す方法を見つけることが重要です。
自分の長所と短所を受け入れる
自分自身の長所を認識し、それを受け入れることは自己受容の大切な一歩です。しかし、それと同時に短所や改善点も受け入れることが、真の自己受容へと繋がります。自分の完璧でない部分を受け入れることで、自己受容の旅はさらに深まります。
比較を避け、自分のペースで成長する
他人と自分を比較することは、自己受容の障壁となり得ます。自分だけのペースで成長し、自分自身の道を歩むことの価値を認識しましょう。自分の成長や成功を他人と比べず、自分自身の進歩を喜ぶことが大切です。
自己受容を促進する活動に参加する
ワークショップやグループ活動に参加することで、自己受容を促進するサポートを受けることができます。例えば、瞑想やヨガ、アートセラピーなどは、自己理解を深め、自己受容のプロセスを支援する素晴らしい方法です。

過保護な親の元で育っても大丈夫

過保護な親に育てられてもちゃんと自分と向き合う術はあります。インナーペアレントの状態がいいというのは自分を見つめることと、見つめられるこの二つのバランスがいい状態のことです。
親から見つめられるだけではそこに自分の思いや意見が埋もれてしまいます。なので自分で出来ることは、「自分のネガティブな思いに対して自分自身で見つめてみる(向き合ってみる)ことです。
自己受容がとても大事なんです。
子供自身の自己受容の仕方
子供が大きくなってからでも自己受容することはできます。辛い・悲しいなどの自分の感情の時にそれを認めないのではなく、自分でもその感情をあえて認めるように語りかけるのが大事です。
「辛いんだよね」「辛いて言っていいんだよ」などです。
大事なのは自分の中で出てくるマイナスな感情に気づくたびに認めてあげる!自分の感情を受け入れることが「自己受容」です。
自分の感情と素直に向き合うことで人は強くなれます。またそれは自分以外の人に対しても受容できることになります。ありのままの自分を受け入れる、相手のそのままの感情を受け入れるというのが大事なんです。
親が子供を受容してあげることも大事
子育ての中で親の過保護や過干渉ではなく、そのままの子供を受け入れることを意識して接することが大事です。何か問題が起こった時にしてはいけないことをしっかり教え、その中でもどうしてそんな気持ちになってしまったか、どんな気持ちがそうさせてしまったのかという子供の感情を受け入れましょう。
【例えば子供が】
自分の子供が夜遊びや不良と付き合って悪いことをした、万引きをした、自傷行為をしたなどとします。「子供のそのままを受け入れる」ということは、悪いことをしたことを受け入れることではありません。
やってはいけないことをしたことについてはしっかり叱り、どうしてそんな気持ちになったかというところを見てあげてください。
●親が忙しくて寂しかったから
●友達を断るといじめられるから怖かった
など、どうしてそんなことをしたのかという気持ちの部分をしっかり認めてあげて受け入れて寄り添う親の気持ちがとても大事です。
決して言ってはいけないのは、次のような事です。
●自分の子供を正当化して、周りを悪く言う。
●あなたそんなことをするような子じゃないとしたことをも認めない。
●たまたま付き合いでしちゃったのよね、と状況をまったく把握しようとしない。
このような事を理解したうえで、親の過保護や過干渉が子供のインアーペアレントを受容のない状況になっていないか、親も意識して考えることも必要です。
親は過保護より子供を受容するのが大事

自分のことをわかって欲しいとか、認めて欲しいという承認欲求というのは人にはあります。その気持ちが満たされることで人は安心したり、自信が持てたり、心の余裕を持てることにもなります。
それが成長過程ではとても大事なことだということを忘れないでおきましょう。そして、親は子供と向き合う事と同じくらい、親としての自分と向き合うことも子育ての中では大事な事のような気がします。
bitomos編集部プロフィール
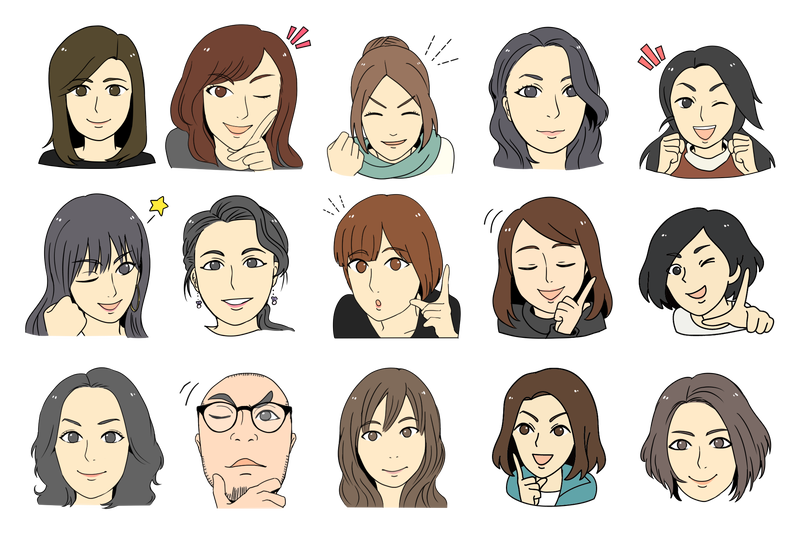
そのライターの経歴や性格を知れば、今後どんどんbitomosの記事を読むのが面白くなるかも!?この記事ではライターそれぞれの自己紹介と、記事を彩るゲストキャラクターたちを紹介していきます。あなたのお気に入りのライターが見つかりますように♡